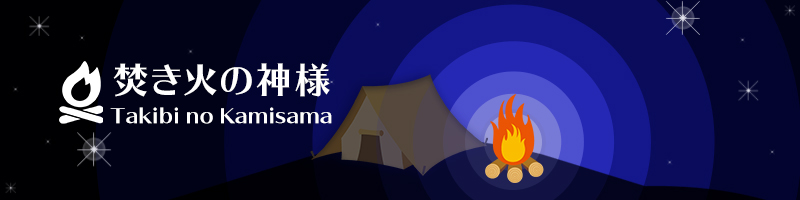そんな疑問にお答えします。
朝晩の冷え込みが激しくなり、もう冬がそこまで近づいてきています。
冬キャンに欠かせないのが、お湯です。
食器を洗う時に使ったり、温かい飲み物を飲むときに使ったりと使い方は様々。
焚き火でお湯を沸かすことについて、私は苦い経験があります。
キャンプ場にて温かいコーヒーが飲みたく、焚き火でお湯を沸かしていました。
お湯がなかなか沸かずせっかちな私は、沸騰する前にお湯をマグカップに注ぎます。
インスタントコーヒーは溶けない、お湯は冷たい、しかも美味しくない。
悲惨な目にあいました。
私みたいに悲惨な目に合わないために、この記事では焚き火で素早く湯沸かしするコツを紹介しています。
焚き火だけではなく、家庭でも素早く湯沸かしが出来るようになります。
これを知っていると知らないとでは大きな差がでますよ。
最後まで読んで焚き火で素早くお湯を沸かすコツを覚えていって下さい。
目次
素早く湯沸かしするには、基本が大切‼

ごくごく当たり前のことですが、何事も基本が大切です。
基本が出来ていないと、湯沸かしするのに沢山の時間と資源を使用します。
まずは、基本をマスターしましょう。
ヤカンやなべの底の水気をふき取る
私はよくやってしまうのですが、「焚き火で水気が飛ぶからいいや」と思い、ヤカンなどの底の水気を拭かずに焚き火の火にかけます。
この行動が一番ダメなことです。
底についた水滴を乾かす分だけ、湯沸かしに時間がかかります。
ヤカンなどの水は拭き取ってから、焚き火にかけるようにしましょう。
底の面積が大きなアイテムを使う
底の面積が大きいと炎や熱の触れる面積が大きくなり、アイテム全体に早く熱が行き渡ります。
アイテム全体に熱が行き渡ると、熱効率が高くなり湯沸かしが早くなります。
例えば鍋で15°Cの水を2リットル沸かした場合、24cmの鍋だと沸騰するのに約7分必要です。
それに対し、16cmの鍋だと沸騰するまでに約11分かかってしまいます。
底が平らで、底面が広い方が湯沸かしし易いアイテムです。
蓋(ふた)をする
蓋をするのと蓋をしないとでは、大きな差です。
蓋をして湯沸かしをしたときの方が、蓋をしないで湯沸かしをしたときより、13.2%も時間を短縮して湯を沸かすことができます。
理由は簡単。
蓋をすることにより湯気となって逃げてしまう熱を逃がさず、湯沸かしに使用することが出来るからです。
撹拌(かくはん)させる
水の対流が発生していると、水温上昇が大きくなる傾向にあります。
つまり、湯沸かしするときにグルグルと水をかき混ぜれば、早く湯が沸くという事です。
撹拌しながら湯を沸かすと、加熱時間が5%短くなったという実験結果もあります。
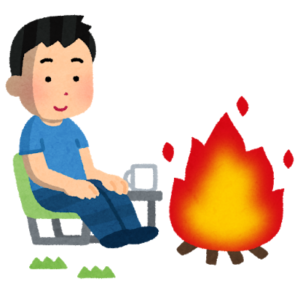
実際に撹拌の効果が最も期待できるのは、点火直後の水温上昇期の時です。
要するに、点火して30秒間だけ撹拌すればいいのです。
材質を選ぶ
湯沸かしする道具の材質を選ぶ事も、素早く湯沸かしするのに大切な事です。
モノには「熱伝導率」という、熱の移動のしやすさを規定する数値を持っています。
熱伝導率が大きければ大きいほど、熱を伝えやすくなります。
つまり、熱伝導率が大きいアイテムを選べば、湯沸かしの時間が短くなります。
素材別の熱伝導率
銅:398W/m・k
アルミニウム:236W/m・k
鉄:83.5W/m・k
銅が一番熱伝導率が大きいので、銅が一番早く湯沸かしできます。
しかし、銅は非常に重い金属です。
銅は持ち運びが大変ですので、2番目に熱伝導率が大きいアルミニウムを選択することをおススメします。
湯沸かしにあった熱源は何?

湯沸かしを素早く行うコツは、理解できたと思います。
今度は湯沸かしに必要な熱源のことも考えていきましょう。
湯沸かしに適さない熱源もあります。
炭
家のガスコンロでお湯を沸かした事がある人なら、お湯が沸くのに10分くらいかかる事は知っているはずです。
家でお湯をわかす感覚で炭火でお湯を沸かすと、非常に痛い目にあいます。
湯が沸くまでに、時間がものすごくかかってしまいます。
火加減にもよりますが20分以上はかかるでしょう。

それは、炭が遠赤外線を発してモノを温める熱源だからです。
遠赤外線は、モノをじっくり時間をかけて温める性質があります。
肉や野菜はじっくり焼いた方が美味しく焼けますが、水をじっくり温めて湯を沸かされても困ります。
炭は湯沸かしに不向きな熱源と言えるでしょう。
薪
一昔前は、お風呂は薪で沸かしていました。
薪は火力が強く、入手性もいいので湯沸かしに適した熱源です。
薪の中で特に火力が強い、松の薪が湯沸かしにはおススメです。
松には多くの油(まつやに)が含まれていますので、着火もしやすい。
燃焼時間も長く、大量のお湯を沸かす事も問題なくこなします。
焚き火で湯沸かしをしている動画ですが、水を入れている道具は空き缶です。
空き缶を使い湯沸かしするなんて、誰も思いつかないアイデアです。
出典:YouTube
バーナー
「薪なんてもう古い。」
「今はバーナーの時代さ。」
こんなことを言えば怒られそうですが、バーナーを使うキャンパーが増えていることは確かです。
バーナーは屋外でも安定した火力で使えますし、着火もカンタン。
薪の炎の温度は約700℃〜900°Cに対して、バーナーの炎の温度は約1800℃で薪の2倍の温度です。
中には、湯沸かしに特化したバーナーもあります。
バーナーで湯沸かしを行えば「薪の半分の時間で沸く」とは言えませんが、この中で一番早く湯沸かし出来る熱源になります。
バーナーを使用して湯沸かしている動画です。
バーナーを使用する時の注意点や、湯沸かししたときにかかる時間などがアップされています。
出典:YouTube
道具で変わる湯沸かしの時間

ここまで読めば湯沸かしのコツ、湯沸かしに適した熱源の事をマスターできるでしょう。
最後に素早く湯沸かし出来る道具のことも、考えていきましょう。
やはり、身近にある「あれ」が一番適しているのかなぁ。
やかん
湯沸かしの道具と言えば、真っ先に「やかん」を思い浮かべるでしょう。
もともとは中国の注ぎ口と取っ手のある、生薬用の加熱器具が発祥とされています。
日本では、薬を煮だすのに用いられたもので薬鑵(やくくわん)と呼ばれていました。
「ヤククワン」がなまって「ヤククヮン」に転じ、「ヤクヮン」「ヤカン」へと変化したと言われています。

やかんがいつから使われたのかは、明確な事は不明です。
しかし、1603年に発行された「日葡辞書(にっぽじしょ)」には、やかんは「今まで湯を沸かす、ある種の深鍋の井意で用いられている」と記載されています。
日葡辞書とは
ポルトガル語で説明を付けた日本の言語の辞典のことです。
イエズス会によって、1603年から1604年にかけて長崎で発行されました。
人群(ひとむ)れ騒(さわ)ぐ江戸幕府。
歴史の授業で1603年をこう覚えた人が多いのではないでしょうか。
1603年と言えば徳川家康が江戸幕府を開いた年です。
約420年前からやかんは、湯沸かしに使う道具とされています。
やかんは湯を沸かす道具として私たちのDNAに刻まれているのですね。
鍋
鍋で湯沸かしする人も増えています。
鍋とやかんで底の面積をほぼ同じにして1Lの水を沸騰させると、やかんの310秒に対し鍋は304秒となりました。
鍋の方がやかんに比べ1.9%時短になります。
鍋の底はやかんに比べ形が平らであるため、炎がはみ出さず部分が少なく、加熱の効果がよくなったからだと考えられます。
「湯沸かしの最強道具は鍋できまり」と言いたいところですが、そうとは言えない部分もあります。
鍋には、取っ手が付いていて取っ手はプラスチック製が多いです。
焚き火で取っ手がプラスチック製のモノを使用すると、焚き火の火で取っ手が溶けてしまいます。
取っ手が金属製の鍋を選べば、それが湯沸かしできる最強の道具です。
圧力鍋
水は1気圧で100℃で沸騰します。
「気圧をあげれば100℃以上で沸騰でき、湯沸かしの時間が短くなるのではないの」と気づいた人は、優秀な人です。
圧力なべを使えば、内部の圧力をあげることができますので、湯沸かしの時間が短縮できます。
メーカーによりますが圧力鍋は蓋と本体を密着させ、だいたい内圧が2気圧、沸点は120℃ぐらいになっています。
20%沸点温度が上がる事によって 湯沸かし時間が約1/3になります。
火を消してから、約10分ぐらいは100℃以上の温度を保つことも可能です。
火にかける時間が短くなり、薪も節約することができます。
しかし、圧力なべはとても重く、強硬なアイテム。
周りの景色になじまなく、キャンプに持っていくことを考えてしまいます。
「どれを選ぼう」焚き火で湯沸かしをするアイテム5選

焚き火で湯沸かし出来るアイテムを見ていきましょう。
湯沸かし出来るアイテムといっても色いろなタイプがあります。
寸胴タイプ、縦長タイプ、やかんタイプなど。
どれが自分のキャンプスタイルにあうのかなぁ。
アルミキャンピングケットル UH-4101/キャプテンスタッグ
この投稿をInstagramで見る
出典:Instagram
熱伝導がいいアルミニウムでできています。
アルミニウムだと少し頼りない気がしますが、安心してください。
アルマイトという特殊な表面加工を施していますので、耐食性、耐摩耗性に優れています。
取っ手をしっかりと立たせてくれるので、湯を沸かしている時取っ手が熱くなるのを軽減してくれます。

SPEC
サイズ:130㎜×150㎜4×高さ77㎜
重量:137g
容量:約700ml
材質:アルミニウム
アルミキャンピングケットル UH-4101を実際に使用している動画です。
評価ポイントも解説しています。
出典:YouTube
ケトルNo1 CS-068/スノーピーク
この投稿をInstagramで見る
出典:Instagram
ケトルなの?
それとも鍋なの?
どちらともいえないフォルム。
このフォルムは、スノーピークが一番使いやすい形状は何かと考え抜いて設計されたケトルです。
洗いやすいように余計な凹凸(おうとつ)がない、シンプルなデザイン。
お湯が注ぎやすいように湯口を設け、蓋を取ればラーメンなどを作れる鍋に早変わり。
上にも吊り手がついていますので煮込み料理も出来ます。
名前の通りNo1のケトルで間違いなしです。
SPEC
サイズ : 直径120㎜×高さ80㎜
重量:255g
容量:0.9L
材質:0.4㎜厚のステンレス
ケトルNo1 CS-068/を解説している動画です。
細部までケトルNo1 CS-068を見ることが出来ます。
出典:YouTube
ファイアープレイスケトル/コールマン
この投稿をInstagramで見る
出典:Instagram
縦長タイプのケトルです。
高い耐久性を誇るステンレス製で出来ているファイアープレイスケトルは、直火にガンガンかけても大丈夫です。
注ぎ口には異物の侵入を防ぐ蓋がついている為、お湯にススなどの異物が入りません。
吊り下げ用のハンドルもついていますので、吊り下げても使用できます。
あまりにも頑丈なので、火に近づきすぎてススで真っ黒だよ。
そんな時は、重曹で洗えばススが簡単に落ち、光沢が元に戻ります。
SPEC
サイズ:13㎝×22㎝×高さ23㎝
重量:約570g
容量:約1.6L
素材:ステンレス
ファイアープレイスケトルの解説動画です。
動画の後半にはケトルを選ぶときの注意点なども説明しています。
出典:YouTube
グランマーコッパーケトル (小)/ファイヤーサイド
この投稿をInstagramで見る
出典:Instagram
使えば使うほどに風合いが増す銅製のケトルです。
底広のデザイン、熱伝導の良い銅の組み合わせでお湯が早く沸き、冬キャンに大活躍。
一枚の銅の板から職人さんが80もの工程を得て丁寧に製作しています。
ケトルを作った職人さんは、こういいます。
「毎日使ってください。ただし手入れをお願いします。」と。
使い方で表情が変わり、赤銅色、飴色、漆黒、自分色に育てる楽しみが、このケトルにはあります。
グランマーコッパーケトルを使い込み、そして育てる。
世界で1つしかない自分オリジナルのケトルを、作っていきましょう。
SPEC
サイズ : 直径180㎜×高さ240mm
材質 :真鍮(内側:スズメッキ)
容量 : 約3.3リットル
重量:1.1㎏
グランマーコッパーケトルの製作風景の動画です。
職人さんが心を込めて製作していることが伝わってきます。
出典:YouTube
大型吊りケトル/ロゴス
この投稿をInstagramで見る
出典:Instagram
保温性に優れているステンレスを採用し、容量3Lも入る大型のケトル。
大人数のキャンプでも安心して使える容量で、何度も沸かす必要がありません。
製品名の通りクワトロポットに吊るして湯沸しが出来ます。
驚いたことに大型吊りケトルは、IH対応です。
アウトドアだけではなく、ご家庭でも使えます。
開口が広い寸胴型のケトルの為、洗うのがカンタンです。
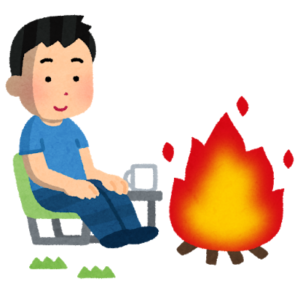
SPEC
サイズ:24.5㎝×18㎝×20.5cm
総重量:580g
容 量:3リットル
素材:ステンレス
大型吊りケトルを使用している動画です。
アウトドアで達磨(だるま)ストーブを使い、お湯を沸かすとは驚きです。
焚き火で素早く湯沸かしできるコツ&湯沸かしに使うアイテム5選:まとめ

まとめとしまして
- 素早く湯沸かしするには、基本が大切‼
- 湯沸かしにあった熱源は何?
- 道具で変わる湯沸かしの時間
- 「どれを選ぼう」焚き火で湯沸かしをするアイテム5選
を紹介してきました。
湯沸かしを素早く行うには、色いろとノウハウがあることが再認識できました。
湯沸かしする時間を短くすることも大切ですが、湯が沸くまでの時間を楽しんでみたらいかがでしょうか。
キャンプの醍醐味は、不便な事や過酷さを楽しむ事なのですから。